あなたは確かにアニメや日本文化に関連するものの中で浴衣(yukata)を見たことがあるでしょう。この衣装は、夏に一般的に着用され、より快適で軽い素材で作られています。浴衣は男性と女性の両方が着ることができ、スタイルに大きな違いはありません。
浴衣は、男性、女性、子供を問わず着用できるカジュアルな着物スタイルです。浴衣の生地は綿または化繊です。帯(布製のベルト)と呼ばれるバンドで体に結び付けられた、優雅なローブのようなものです。しかし、このスタイルはどのようにして生まれたのでしょうか?着物と浴衣の違いは何ですか?この衣装について詳しく見てみましょう。

目次
浴衣はいつ、どのようにして登場したのでしょうか?
ゆかたはもっと伝統的な服装であり、しかし特定の場面や祭りにおいてはその服装を使用することが一般的です。この服装は、ゆかたびら(湯帷子)に由来しており、麻(カンナビス・サティバ種の植物)で作られ、温泉(おんせん)に入るために貴族の人々によく使われていました。
平安時代にはすでに行われていましたが、日本で綿の使用が増加した江戸時代(1603~1868)に普及しました。布地に綿が使用されるようになったのは799年頃と考えられています。難破した中国人によって日本に運ばれた。綿花栽培は増えるばかりだった。伝統的な着物の最大の生産者となる。
浴衣とは文字通り「水着」を意味し、当初はそれが目的だったはずだ。浴衣は一時期、入浴後や就寝後に着る寝室着としてのみ使われていました。しかし、その衣装は最終的にはフェスティバルでも席巻することになりました。伝統的な浴衣は、ジーンズと同じように藍の葉(藍色を生み出す植物)で生地を染めたもので、青から少し白まであります。

しかし、現在では使用できるモデルの種類が豊富になり、アクセサリーなどを使用してさまざまな組み合わせを行うことができます。現在、この服装に関して従うべき基準はあまりありません。男性の浴衣は暗めの色ですが、女性の浴衣はよりカラフルで花柄のものが多いです。
人々が日本の祭りや花火大会(Hanabi Taikai)で浴衣を着ることはまだ一般的です。また、夏に行われる他の伝統的なイベントでも着用されます。温泉地では浴衣を自由に着用します。また、旅館や温泉(onsen)でも見られます。
浴衣と着物の違いは何ですか?
着物は文字通り「衣服」を意味し、一般的に結婚式、葬儀などのよりフォーマルな機会に使用されます。かつては男性が日常的に着用するのが一般的でした。ただし、現在は特定の正式なイベントに重点が置かれています。
着物は、男性用と女性用の両方が一般的に控えめな柄であり、着物を着るためには、着用する人の場面、季節、性別、親族の度合い、または婚姻状況などのマナーを守る必要があります。
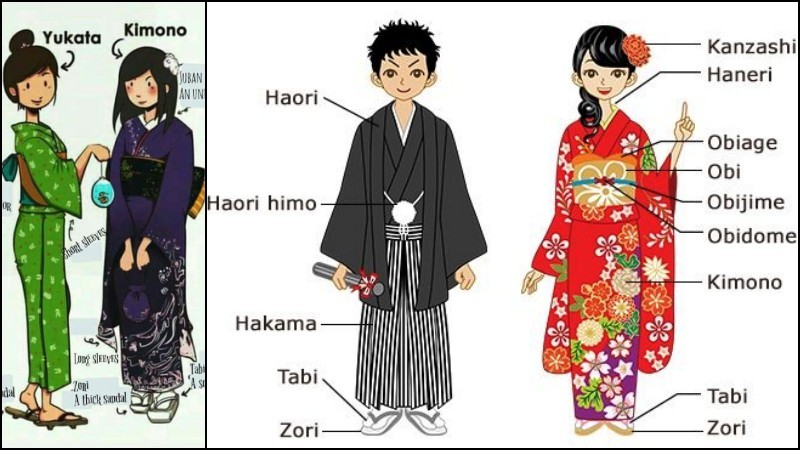
男性と女性の着物の造形は袖に関して若干異なります。男性の着物は脇の下で縫い付けられ、女性の着物は前腕が開いています。生地には、綿、シルク、さまざまな合成繊維のオプションがあります。
浴衣との違いはその呼び方から始まり、浴衣の語源は「湯」(ゆ)と「帷子(かたびら)」(下着)です。服装に関してすでに述べたすべてに加えて、伝統的な浴衣は通常標準的な綿生地で作られ、夏祭りやパジャマとしても使用されます。着方も違いますし、浴衣もかなり軽くなっています。

浴衣の着方は?
ジャパン・ハウス・サンパウロのウェブサイト (www.japanhousesp.com.br) には、浴衣の着方について段階的に説明されています。
必要になるだろう:
• Yukata : informal summer kimono.
• Obi (帯): ornamental belt used to tie the kimono.
• 2 himos (紐): strips measuring, in general, 240 x 4.5 cm (can be adapted using strips of other widths or thick elastic, as long as they are comfortable and do not slip)
• Shitagi (下着): underwear used to protect the kimono from body sweat. This item is optional and can be adapted with a low-back cotton t-shirt to show the skin through the opening of the eri (衿), the collar.
• Geta (下駄): Japanese clogs. This item is also optional and can be adapted with flip-flops.
1. 位置を合わせます senui 背縫い(背縫い)、背中の中心に縦に縫い目があって、身頃の中心となります。
2. の端を結合します。 eri 縫い目が体の中心にあることを確認し、裾の高さを調整します。
3. 左側のバーの高さを確認してください。 yukata, なぜなら、最終的にはこの部分が一番上になるからです。
4. 左側を重ねた後、右側が見えない位置に配置し、左側を重ねます。足首が隠れるか、動いたときにさりげなく見える丈が理想的です。
5. 結ぶ 腰紐 (腰紐)、ヒップバインディング。体を二重に包み込み、生地を快適な位置に固定するのに十分な程度に締めます。
6. 手を通します みやつくち 身八つ口(身八つ口)とは、女性の着物にのみ存在する袖の下の開口部で、 ohashori (おはしょり)、余った生地の折り目も女性の着物にのみ存在します。生地を裏表に並べます。
7. 修正してください eri 首の下の骨の近くの前部に「Y」字型に切り込み、後ろに拳ほどの大きさの開口部を残します。
8. マチェーテ munahimo (胸紐)、胸の縛り。 2回転させて深呼吸し、生地の位置を固定するために押します。こうすることで、着物を着ている間も快適に呼吸することができます。
9. 生地の裏と表を滑らかにします。 munahimo からです ohashori、結んだ後に見えるように、表と裏にもあります。 obi.
10. 可能であれば、着物の前面、側面、背面の縫い目を揃えてください。この部分は練習が必要ですが、成功しなくても落胆しないでください。できる限り使用して、時間をかけて完成させてください。
帯の結び方
1. バンドを半分に折り、余った部分を残して、肩の高さより少し上で斜めに結びます。
2. バンドを矢印の形に開き、体に応じてバンドの上部をバストの中央付近またはそのすぐ下の高さに合わせます。 2 回転させてバンドを締め、吸入したときと同じ方法で吸います。 munahimo.
3. 斜めに折ります obi ノードの実行を容易にするためです。
4. 本体の前側で輪を作ります。肩の寸法を使用して折り始めます。 tare 結び目から残った一番長い部分を端を揃えて何度も折ります。
5. ほぼ中央に配置します。 tare ノードの上。横に半分に折り、さらに上下を半分に折り、アコーディオンを作ります。
6. 半分に折ったバンドの最初に残した余った部分を、先ほど作った結び目の下に通します。もう 1 回回して固定し、残ったものを丸めて、内側に隠します。 obi、ループの側面を中央に配置します。
7. 慎重に回転させて、 obi邪魔にならないように左から右へ eri そして弓を背中の中央に置きます。
8. を配置します。 入手する - 下駄とその他のアクセサリー。
