家に読まない本が山積みになっている人も多いでしょう。これは非常に一般的であるため、日本人は頻繁に本を買うのにまったく読まない人を指す言葉を持っています。この言葉は「積ん読」と呼ばれ、多くの好奇心と興味深い情報がこの記事で取り上げられます。
「積ん読」は、読みの表意文字「読」と積み重ねるという意味の表意文字「積」に由来しています。本を溜め込む人、あるいは膨大な量の本をストックしたり山積みになったりする人のことを指します。
この癖はよくあるもので、私自身も日本でマンガを山ほど買ったのですが、今日まで一度も読んだことがありません。日本は読書を大切にする国なので、「積読」という言葉の存在も理解できます。その起源についてはほとんど知られていません。
目次
積読の言葉の由来
この言葉は明治時代(1868-1912年)から存在したと考えられており、文字通りの山積みの本を指す場合もあれば、本を買っても全く読まない人を指す場合もあります。この単語の最も古い出現の 1 つは、1879 年のテキストにあります。
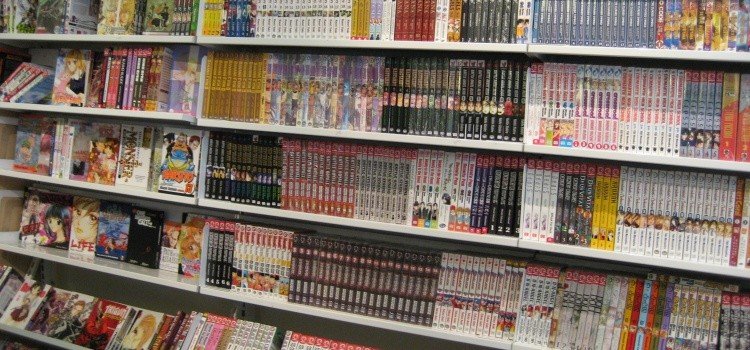
「tsundoku」という言葉を文字通りに考えると、その表現が「本の山を読む」と言っているように思えるかもしれません。本当にその言葉の目的は、読まずに買った本と関連付けたダジャレを作ることです。
Tsundoku 動詞から来た ツンデレ 「積んでおく」という言葉は、一か所に積み上げることを意味します。 読書 【読書】読書という意味です。 tsundoku と tsundoku は非常に似ているため、語呂合わせであることに注意してください。
「tsundeoku」[積んでおく]という動詞は、動詞tsumu [積む](積む)とoku [置く](置く)の結合です。このため、「tsundoku」[積ん読]という表現は、本を積んで読まないという意味になり、全く理にかなっています。
積読 - 日本の本を積み重ねる
日本では本を集めるのはスペースがなくて難しいのではないかと想像する人もいるかもしれません。実際には、日本には大都市とアパートだけで、一部の人が考えているほどスペースは狭くありません。とはいえ、自宅に図書館を持つのはそう簡単ではありません。
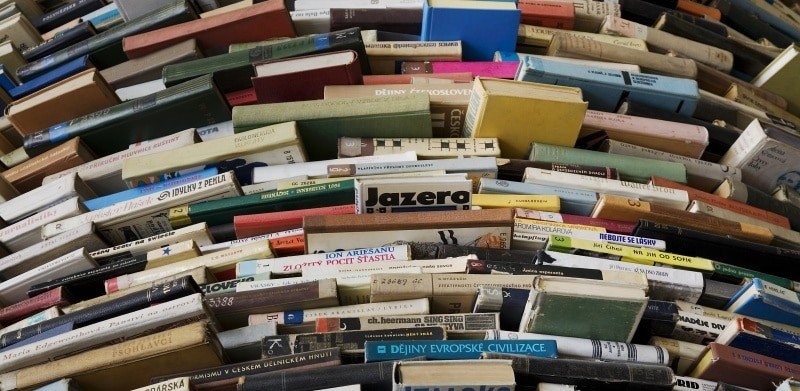
日本人は実用性とミニマリズムを好みます。本を集める習慣があまりなく、週刊誌を捨てて古本を寄付したり店に売ったりする人もいる。古本やマンガの図書館は無数にあり、とても安いです。
それでも、本の積み重ねは珍しくありません。なぜなら、整理整頓が苦手な日本人もおり、家の中に物をただ積み重ねることがあるからです。さらに、外出しないことが多いひきこもりは、自分の部屋が乱雑になることがよくあります。
日本では、読まずに本を集めるこの現象は非常に一般的です。人々は週刊誌で漫画を丸ごと読んでしまい、必ずしも漫画に触れることなく、単に巻を分けて購入してコレクションとして所有するだけです。

日本で消費される読書の約70%は日本語由来のものです。毎年10万本以上の新作が発表されており、日本はランキング4位となっている。日本は毎年約200億ドルを書籍から生み出しており、その半分は雑誌です。
たとえ本を読むことが不可能な場合でも、購入した本の存在は非常なエクスタシーを生み出し、読み切れる以上の本を購入することは無限に到達する魂に他なりません...私たちはたとえ未読であっても本を楽しみ、その存在だけで安らぎを与えます。
エドワード・ニュートン
積読という言葉が世界に与えた影響
世界中の読者の間で「積ん読」という言葉は非常に人気になりました。カラオケ、津波、オタクと同じように、人々がこの言葉を他の言語に持ち込んだことがわかりました。
この言葉を電子書籍、映画、DVD、ゲーム、スマホアプリなどに使っている人もいます。物をため込んで全く使わないということは、誰にでもよくあることです。私たちの生活はとても忙しいので、つい不必要に物を買ってしまいます。

必死になって何かを買ったのに、「要らない、使っていない」と言った経験はありませんか。本の場合は、本が山積みだったり、本を読む時間がなかったり、ただ怠け者だったりすると、このようなことはさらに起こりにくくなります。
同様の意味を持つ別の言葉としてビブリオマニアがあります。これは本を集めて蓄積するのが好きな人を指します。大きな違いは、積読は単に本の山や本でいっぱいの部屋を指すこともあることです。
この記事で「積ん読」の意味がさらに詳しく説明できれば幸いです。気に入っていただけましたら、共有してコメントを残してください。最後に、お勧めの記事をいくつか以下に残しておきます。
