読むことは人生を変えることができる行為です。また、国の良い教育のための原動力でもあります。本は、読まれることで読む人の心に蓄積され、読書が深まるにつれて読者の人格が変わっていきます。本は、特定の文化のニュアンスをより良く理解するためのツールでもあります。日本文化は、良い文章と、特に良い本からよりよく理解されることができます。
この記事では、いくつかおすすめします。読書が好きではない人は、知識が私たちをより良い人間に変えると考えて、この習慣を作り始めてみることをお勧めします。すでに気に入っている方は、以下でコメントする提案を楽しんでいただければ幸いです。残念ながら、ブラジルではしっかりとした読書習慣がまだ確立されていません。でも、もしかしたらいつかはわかるでしょうか?

ここをクリックして、日本語を学ぶのに最適な本に関する記事をお読みください!
このリストに記載されていない本に関する提案がある場合は、お気軽にコメント欄でお知らせください。あらゆる提案を歓迎します。
ということで、リストにいきましょう!
目次
1. 日本人 - セリア・サクライ
日本文化について学ぶための素晴らしい本の一つが、セリア・サクラ●著の日本人です。これは日本のさまざまな側面を集めたコンペンディウムで、神話、農業、経済、社会、家族、歴史、政治、ポップカルチャーなどが取り上げられています。理解しやすく、各章は日の出の国に関連する主な要素を質と活力をもって要約しています。
日本を日本たらしめるものについての全体的な概観を求めている人には、読みやすく楽しい(写真、グラフ、イラストが豊富に含まれる)Os Japoneses(2007年)、出版社コンテクストが間違いなく最良の選択です。
以下は、ジョーのプログラムに関する著者のインタビューからの抜粋です。
The Japanese - 桜井セリア on Programa do Jô 1/2 - YouTube
The Japanese - 桜井セリア on Programa do Jô 2/2 - YouTube
2. 簡潔な日本の歴史 - ブレット・L・ウォーカー
日本の歴史は戦争、クラン間の争い、封建領主、侍、忍者、皇帝、将軍、そして経済の変革に満ちています。このように豊かで古い歴史を包括するには、それに特化した本が必要です。
簡潔な日本の歴史アメリカ人のブレット・L・ウォーカー著、まさに私たちが探しているものです。日本の先史時代に遡ると、この国はまだ中国人と朝鮮人によって扱われていました。 倭国 (「ドワーフ」王国、意訳)現代に至るまで、この本は、日本や他の世界大国が組み込まれているグローバル化した資本主義世界の自然災害や環境への影響についても学ぶことの重要性によって導かれています。
一般の歴史愛好家に最適です!
3. 日本文化における時間と空間 - 加藤周一
日本文化における時間(と空間)の問題を論じた哲学書。 「現在の文化」として構成されている、つまり物事が経験される瞬間に焦点を当てていることを特徴とする日本社会は、自然の不確実性(津波、地震、火山)によって正当化される、未来への絶え間ない恐怖を抱えています。噴火、台風、将来の原子力災害)の領土。
言語においても、現在を表現する傾向が常に見られます。これは、現在と未来の両方の行動を促す文法形式ます (masu)によるものです。日本語の未来は非常に曖昧で、多くの場合無視されがちです。過去の完了形と現在/未来のための文法構造があります。この点において、なぜそうなっているのかを考えることは重要です。
この本の裏表紙には、このトピックをうまく要約した次の引用があります。
「日本社会のあらゆるレベルで、その傾向が強い。
過去を水の流れに任せて、現在に生きるということ。
風向きに未来を託す。現在の出来事の意味は、過去の歴史と将来の目的との関係とは無関係に、それ自体で定義されます。」
4. 日本文化入門:相互人類学エッセイ - 中川久康
短く、約128ページの本書は、一連のエッセイ/アンソロジーを基にしており、ブラジルのマーチン・フォンテス出版社から出版されています。日本文化入門: 相互人類学のエッセイは、日本文化を西洋、特にフランスの視点から考察する人類学的な本であり、流麗な文章が特徴で、国とその文化に関する知識の向上に大いに貢献しています。
この本はアマゾンや他のオンラインショップで購入できます。実店舗では、特に国の中心地(リオ・サンパウロの外)から遠くの地域では見つけるのが難しいです。
5. 茶の本 - 岡倉覚三
岡倉覚三著『茶の本』は、タイトルとは裏腹に、茶についての本ではなく、日本文化と茶道の伝統を結び付け、この問題に取り組んだエッセイです。古代と近代の間の対立、それは現代の日本にもよく見られる側面です。
禅宗、道教、建築が日本文化に与えた影響や茶道の体験など、他の主題も取り上げられます。
とても内容の濃い本なので、とても読み応えがあります!
6. 論語 - 孔子
孔子は重要な中国の思想家であり、東洋の社会生活の数多くの側面に影響を与えました。忠誠、知恵、従順、権威の理想から家族、政府、心理的問題に至るまで、孔子は東洋の偉人の一人であり、「儒教」として知られる政治的、哲学的、宗教的、社会的教義に名前を付けました。この教えは数世紀にわたり中国を支配し、日本文化とその決定的影響に関してもなお力を持っています。
論語 儒教の最も有名で最も重要な書です。読みたい人は、すべてが現代の日本に当てはまるわけではないことを知っておいてください。しかし、多くの聖句は数世代にわたって受け継がれてきた教えを構成しています。
7. 心理学と東洋宗教 - カール・G・ユング
心理学を愛する皆さんには、日本文化や東洋の考え方をより深く理解したい方のための素晴らしいオプションもあります。
心理学と東洋宗教スイスの有名な精神科医で医師のカール・ユング(分析心理学または元型心理学の創始者)による本書は、情報と哲学的考察が豊富で、分厚い複雑な本です。
ここで、ユングは西洋思想と東洋思想の違いについて語り、仏教、ヒンドゥー教、中国文化、タオ・テ・チン、歴史といったテーマを取り上げ、合理主義(西洋の二元論的思考)に対抗する東洋の一元論の問題を描き出します。
8. 産業化以前の日本文化: 社会経済的側面 - 宮崎伸江
それは、日本文化の 2 つの基本的な側面、つまりハイテクと産業化以前の伝統の共存をテーマとしています。古いものと新しいもの、現代と古いもの、都市のテクノロジーと田舎の自然が混在する社会。この本は人類学、経済学、テクノロジーをカバーするパートに分かれており、合計は 144 ページ強です。
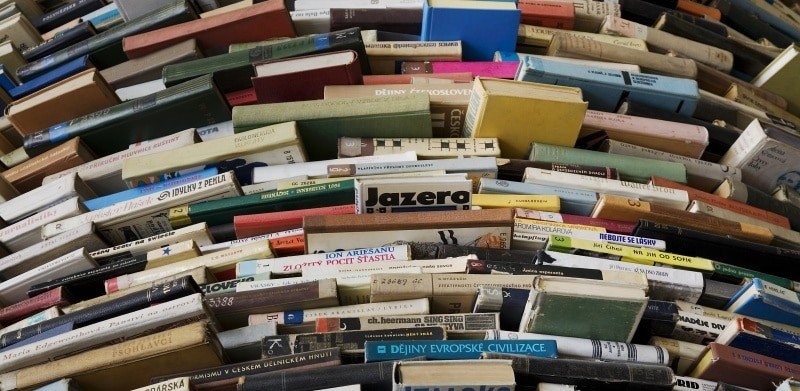
そしてそこに?ヒントは気に入りましたか?コメントしたり、「いいね!」をしたり、ソーシャルメディアで共有したりしましょう!
