伝統的な日本家屋には何があるか考えたことはありますか?この記事では、日本の家にしかない伝統的な機能をいくつか紹介します。日本限定の建築、インテリア、オブジェなど。
日本の住宅の建築やインテリアの特徴の多くは独特であり、それらは古いものではありますが、今日でも多くの住宅に存在しており、日本の歴史と文化の重要な部分であると考えられています。
目次
障子、襖、欄間 - 襖
まずは、現代のアパートや住宅を含め、多くの日本の住宅に存在する引き戸と壁について話しましょう。家の少なくともリビングルームまたは1つの部屋には、1つの部屋を拡張したり2つに分割したりできるドアまたは壁があります。

Shoji これらは、木製で構成され、半透明の紙が詰められたパネルまたは引き戸です。家の内壁と外壁の両方に使用されます。自然光が家の中に入るようにします。
Fusuma 障子のように半透明の紙が張られておらず、壁としての役割を果たすドアや壁の役割を果たす障子であり、装飾が可能であり、秘密の通路や部屋を作ることもできます。

日本で見られる引き戸の利点の 1 つは、リビング ルームをプライベート ベッドルームに変えることです。多くの家は壁と引き戸のおかげでモジュール式になっています。
Ranma 障子や襖の上に設置され、室内に光を取り込むためのパネル。ほとんどの場合、それらは装飾された木材または障子に似たもので作られています。

玄関、縁側、床の間 - 日本のバルコニー
Genkan 伝統的な日本家屋の玄関であり、靴を脱ぐ場所です。小さなホール、バルコニー、ラグのある部屋、または靴を脱ぐ必要があるスペースなどです。また、踏まないようにしてください genkan 裸足でも靴下でも。
玄関の主な機能は、靴に残った道の汚れが家や建物の中に入るのを防ぐことである。そのため、genkanは通常、家の床と高低差があるように作られており、外からの汚れを抑える役割を果たしている。

脱いだ靴は、退室時に履きやすいように正面をドア側に向けて置き、建物内を歩くときは別の靴「うわばき」またはスリッパ「スリッパ」を履くのが一般的です。
こちらもお読みください: 日本の伝統的な靴 10 足
玄関は家の入り口にあるが、古い家のバルコニーの外側には、和式の家を囲む外廊下である縁側があります。縁側は、伝統的に障子の扉や壁を太陽、雨、嵐から守るために使われます。

伝統的で裕福な家屋には、客人を迎えるために設計された床の間もあります。通常、絵画、書道、巻物、盆栽、置物、生け花などの美術品が置かれる場所です。
こちらもお読みください:
tokonomaに関するいくつかのエチケットのルールがあります。その一つは、ゲストを迎える際、tokonomaに背を向けるべきだということです。これは控えめさに基づいており、ホストはゲストにtokonomaの内容を見せてはいけないため、tokonomaを指さすことを避ける必要があります。

和小屋 - 釘のない屋根
日本の大工は高度な大工技術を開発し、釘を使わずに大きな建物を建てることができました。これらの釘のないフレームには、地震に対してより適しているという利点があります。
これらの木材を組み合わせたり、縄で縛ったりしたものは、古い日本家屋などでよく見られます。今日では、建築様式は異なっていても、多くの家は釘で打たれた屋根ではなく、はめ込まれた屋根で建てられています。

畳 - 和室
畳は床や敷物です。 伝統的に稲わらで作られています。地域によってサイズが異なる標準サイズがあります。畳は日本で非常に一般的で、家やアパートは通常、畳のサイズを単位として測定されます。
これらは、床に展開して寝るという伝統的なライフスタイルを表しています。畳は柔らかく自然な足あたりがあり、新しいうちは心地よい香りが漂います。正座(写真)など、幅広い用途や習慣に関連付けられています。

こたつ・ちゃぶ台・座布団
こたつは、電気ヒーターが内蔵された低いテーブルです。 重い毛布で覆われた futon人々はリラックスしたり、食事をしたり、勉強したり、テレビを見たりするために、こたつの下で足を組んで座ります。
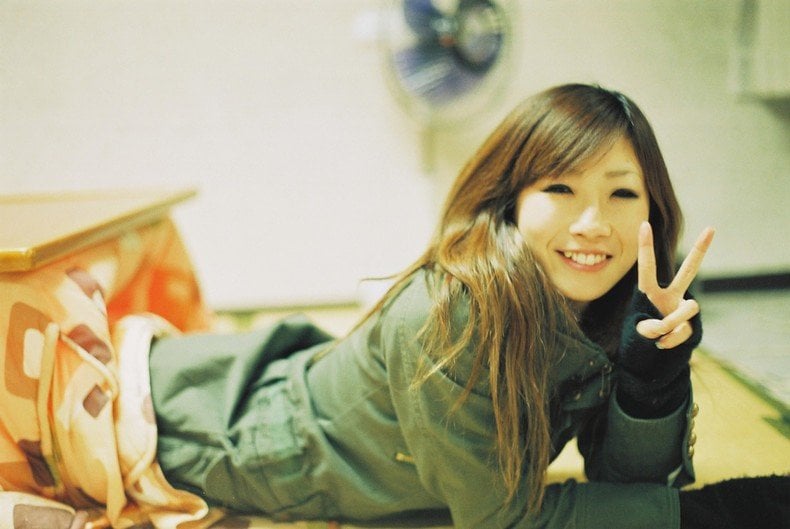
Chabudai 床に座って使用する脚の短いテーブルで、通常はコタツと同じタイプのテーブルです。異なるサイズも可能です。
通常は畳の床で使用されますが、硬い床にも設置できます。家族が座布団に座りながら、ちゃぶ台で食事をしたり集まったりするのが一般的です。
Zabuton 畳の床に座るときに使用する薄い枕です。それらは椅子に相当します。相撲の試合では、観客が投げることで知られています。 zabuton 不評な結果に抗議するためにリングへ。

おふろ - 日本の浴槽
「おふろ」は日本語でお風呂を意味しますが、古代の日本では家にバスルームがなく、人々は毎晩銭湯として知られる公衆浴場を訪れていました。
明治時代になると、おふろは一般家庭に普及し始めました。日本のお風呂は通常、浴室とは別の部屋にあります。つまり、基本的に日本のほとんどすべての家にはバスタブと小さなシャワーがあります。
日本人はレジャー活動としてホットタブを使用し、長湯する傾向があります。一部の家や旅館には木製の風呂が贅沢に備え付けられています。日本ではお風呂に入るのが習慣であり、文化の一部です。
こちらもお読みください:

囲炉裏 - 日本の暖炉
囲炉裏は家の暖房と調理に使用される囲炉裏で、床にある四角い穴で覆われ、その穴の上の天井から吊り下げられ、火の上に鍋を吊るすために使用できるフックまたは「自在鍵」で覆われています。
囲炉裏を備えた現代の家はほとんどなく、ますます希少になっています。日本の田舎の古いレストランにはそれがあります。冬にはどこででも人気があります。

すだれ - 伝統的なカーテン
すだれは、木や竹などの天然素材を横に張って作る伝統的なブラインドです。通常は春と夏に着用されます。
涼しい風を通し、日差しを遮る効果もあります。スダレは古代の技術を使って作られることが多く、鉄製のフックが付いている場合があり、今日の基準から見ると大きく見える場合があります。
ベーシックなデザインがほとんどですが、絹や金糸などの高価な素材を使ったものもあります。

以下のビデオで日本住宅の主な古典的な特徴をご覧ください。
